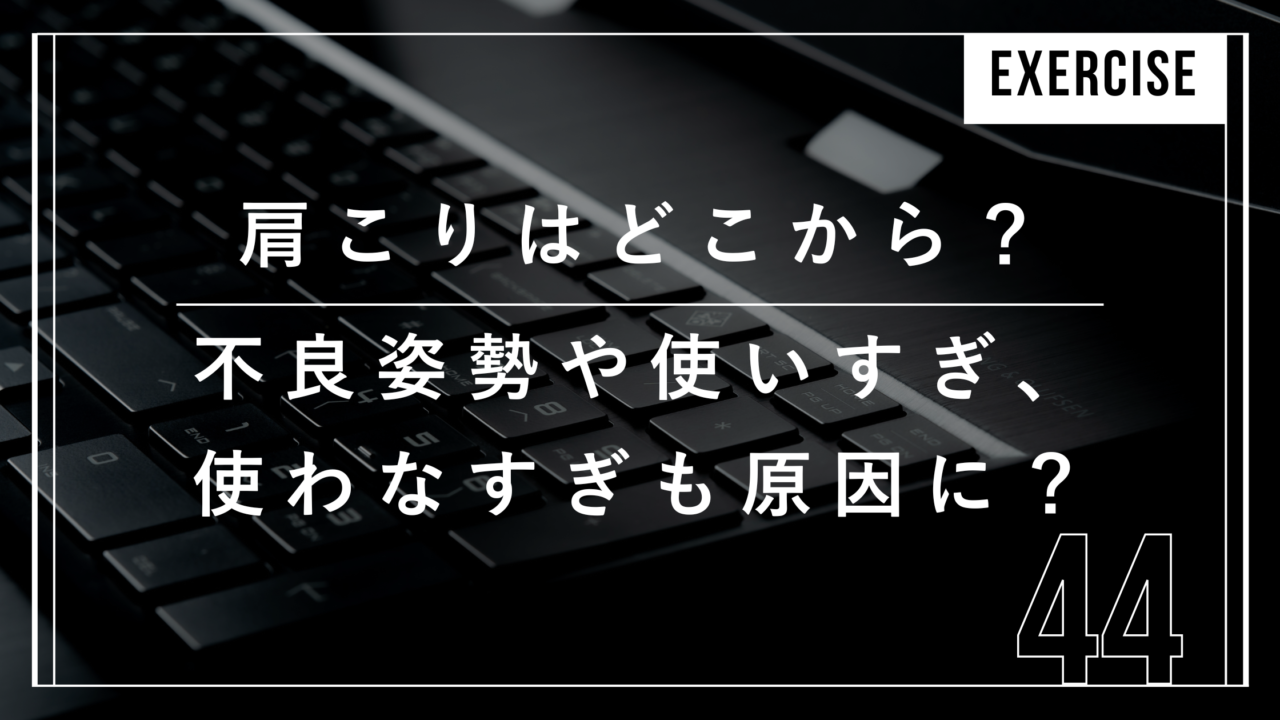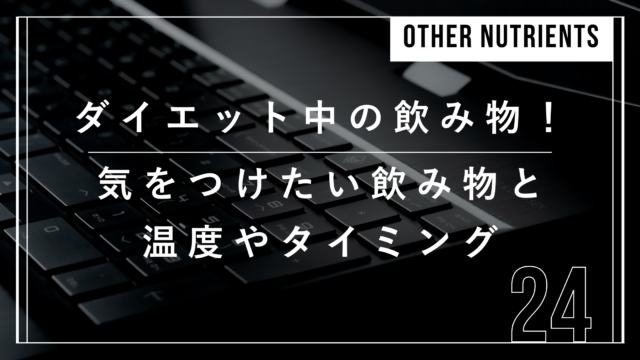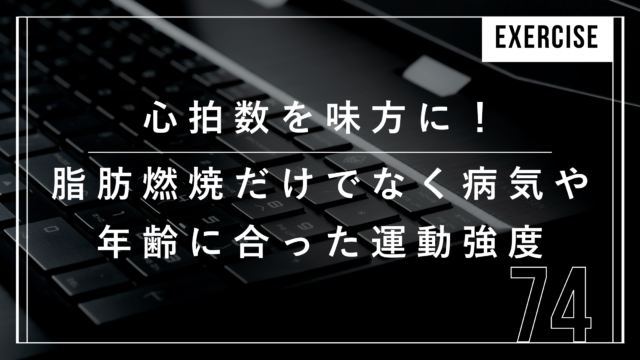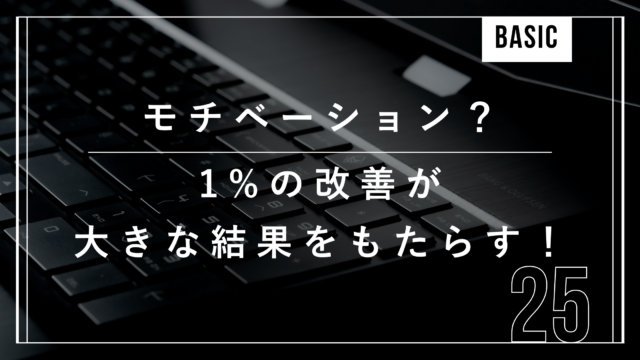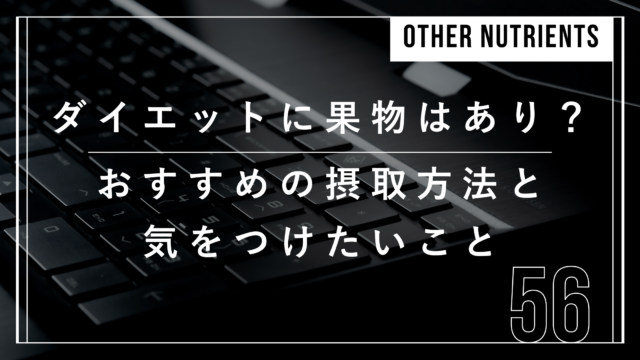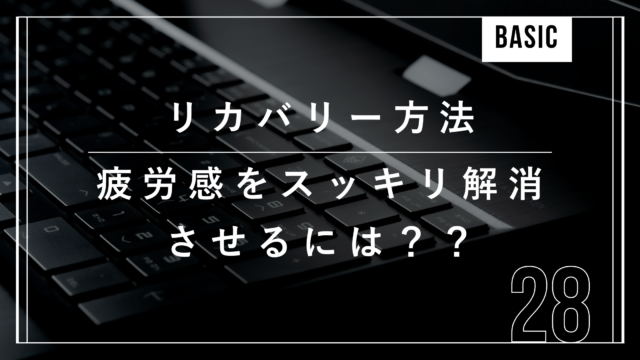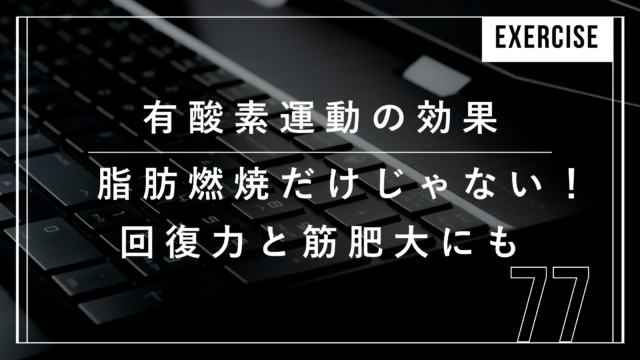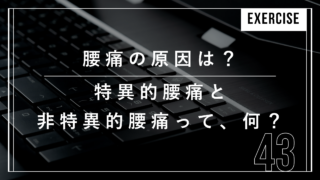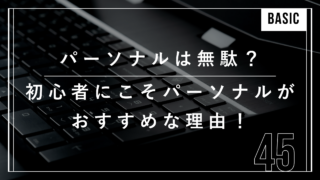「常に肩こりがある…」「ひどい時には頭痛やめまいが…」
こんにちは!新潟県上越市・妙高市を中心に活動しておりますパーソナルトレーナーの矢坂です!
肩こりは、日本人の多くが悩む慢性的な症状の一つです。特にデスクワークが多い方やスマホを長時間使用する方は、知らず知らずのうちに ストレートネックや猫背(巻き肩・円背姿勢) になり、肩こりを悪化させてしまうことが多いです。
また、現代は「ストレス社会」であり、交感神経が過剰に優位になり、自律神経が乱れること も肩こりの大きな原因の一つと考えられています。
今回は、肩こりの原因をしっかり理解し、姿勢の改善や適切な運動・ストレッチで予防・解消する方法 を解説します!
1. 肩こりの原因とは?ストレートネックや猫背との関連性
肩こりの主な原因は、大きく以下の3つに分けられます。
① ストレートネックや猫背(巻き肩・円背姿勢)
「スマホ首」とも呼ばれるストレートネックは、本来S字カーブを描くはずの首の骨(頸椎)がまっすぐになってしまう状態 です。
また、猫背や巻き肩の姿勢が続くと、肩甲骨が外に開いて(外転)、首や肩に過剰な負担がかかります。
✅ 姿勢が悪くなると…
- 首や肩の筋肉が常に緊張し、血流が悪くなる
- 頭の重さ(約5kg)が支えにくくなり、さらに肩こりが悪化
- 肩甲骨の可動域が狭まり、筋肉のバランスが崩れる
→首の角度がまっすぐで5kgですが、15度になると12kg、30度で18kg、45度で22kg、60度では27kgと角度が増すにつれて負荷が大きくなっていることがわかると思います。
② 自律神経の乱れ(交感神経亢進状態)
ストレスが多いと交感神経が優位になり、筋肉の緊張が強くなります。
本来、リラックス状態では副交感神経が働き、血流が改善されるのですが、ストレス状態が続くと肩や首の筋肉が緊張し続ける ため、慢性的な肩こりが生じます。
また、この状態では痛みに対して敏感になることも注意です。過剰に痛みを感じると防御性の収縮が生じて常に筋肉に緊張がかかっているような状態を助長することになります。
③ 血行不良・運動不足
運動不足により、肩や首周りの血流が低下すると、筋肉が硬くなりやすくなります。
かといって無闇に首を動かしたり無理やりストレッチをすると痛めてしまう可能性もあります。日常的に少しづつ動かしたり定期的に入浴をして温めるなどして改善を促していきましょう。お風呂の後のストレッチがおすすめです。
2. 肩こりを予防・改善するための運動・ストレッチ
ここからは、肩こりを改善するための具体的な運動・ストレッチ を紹介します。
① 首周りのストレッチ(僧帽筋・胸鎖乳突筋のリリース)
デスクワークで緊張しやすい首の筋肉をゆるめ、血流を促します。
やり方
- 椅子に座ったまま、片手を頭の横に置く
- 反対側の肩を下げるように意識しながら、ゆっくり頭を横に倒す
- 30秒キープしたら、反対側も同様に行う
- さらに、斜め前に倒したり斜め後ろに倒したりして、色々な筋肉が伸びていくのを感じましょう。
✅ ポイント
- 伸びている部分を意識しながら、息を止めずに行う
- 痛みがある場合は無理をせず、ゆっくりとした動作を心がける
- 手で無理やり倒すのではなく、傾いた頭を軽く抑える程度で
② 肩甲骨を動かす「肩甲骨ほぐしエクササイズ」
肩こりの大きな原因の一つである 「肩甲骨の可動性低下」 を改善する運動です。
やり方
- 両手を肩に乗せる(肘を横に張る)
- 肘で大きく円を描くように回す(前回し・後ろ回し)
- 各方向10回ずつ行う
✅ ポイント
- 肘を大きく回し、肩甲骨をしっかり動かす意識を持つ
- 肩をすくめないように注意する
- 肘の軌道を意識しすぎると肩甲骨が動かなくなる方が多い
→肩甲骨が動いた結果、肘で円を描ける、くらいがベスト!
③ 胸を開くストレッチ(猫背改善)
巻き肩・猫背を改善することで、肩こりの根本的な原因を解消します。
やり方
- 両手を後ろで組み、肩甲骨を寄せるように胸を開く
- ゆっくり深呼吸しながら、30秒キープ
- 余裕があれば、手を後ろで持ち上げる
✅ ポイント
- 背中が丸まらないように意識する
- 肩甲骨を寄せる感覚を大切にする
- 腰が反りやすいストレッチのため、反らない範囲で行う。もしくは軽く腹筋に力を入れて骨盤が過度に前傾しないように注意する
3. まとめ
肩こりは、ストレートネックや猫背などの姿勢の悪化、ストレスによる自律神経の乱れ、運動不足 などが主な原因です。
✅ 予防・改善するためには
- 首・肩周りのストレッチ(僧帽筋・胸鎖乳突筋)
- 肩甲骨を動かすエクササイズ(肩甲骨ほぐし)
- 胸を開くストレッチ(巻き肩・猫背改善)
を習慣にすることが大切です。
特に、デスクワークが多い方は、こまめにストレッチを取り入れることで、肩こりの悪化を防ぐことができます!
また、肩周りの筋肉を過剰に使いすぎた結果肩こりを誘発している方ももちろんいますが、適切なタイミングで適切に筋力発揮をすることができていないことが原因になっている方も多いです。使わないように使わないようにという意識にならないように、正しく使っていく中で症状を和らげていきましょう!(炎症期の方など無理に動かすことを避けた方が良い方もいらっしゃいますのでぜひご相談ください)
私について
新潟県上越市・妙高市を中心にパーソナルトレーニングを提供しています。
理学療法士の国家資格を持ち、解剖学・運動学・生理学・栄養学などの知識を活かし、体の不調改善からダイエット、ボディメイクまで幅広くサポート。