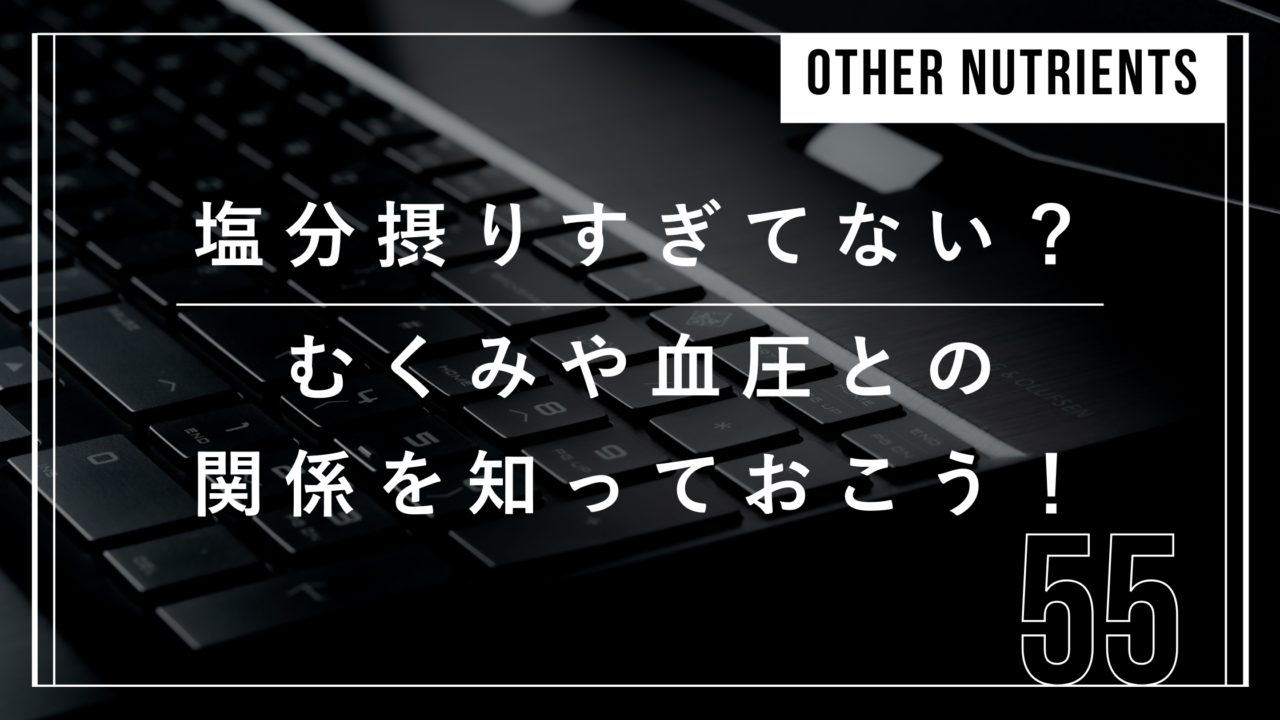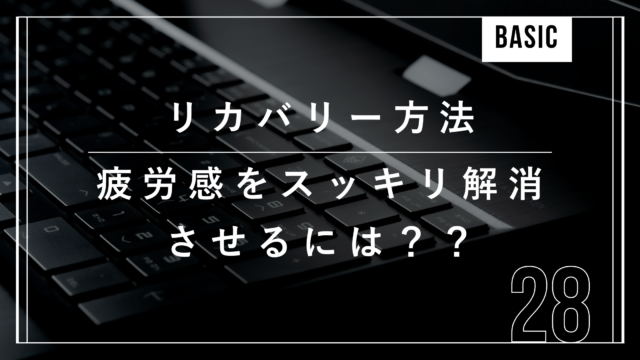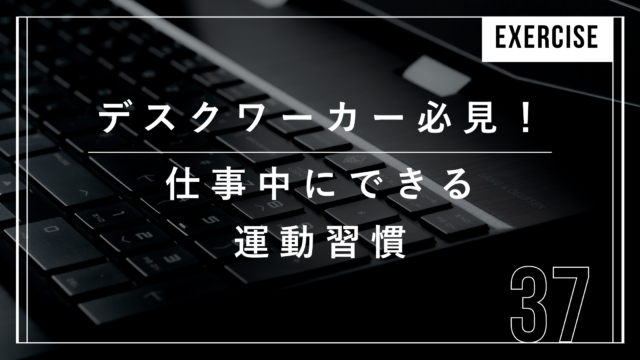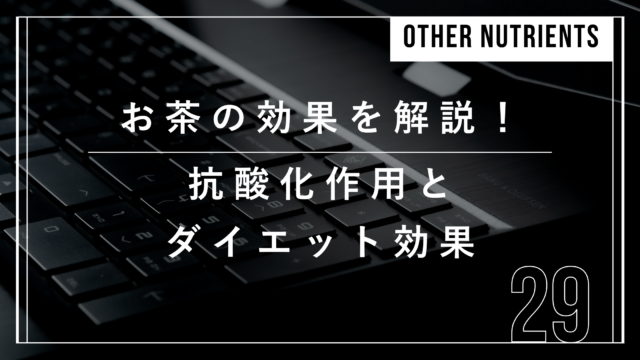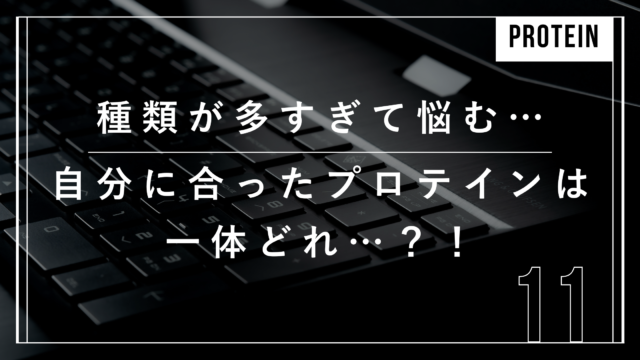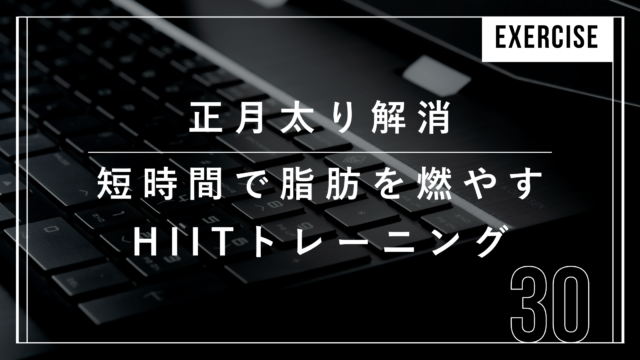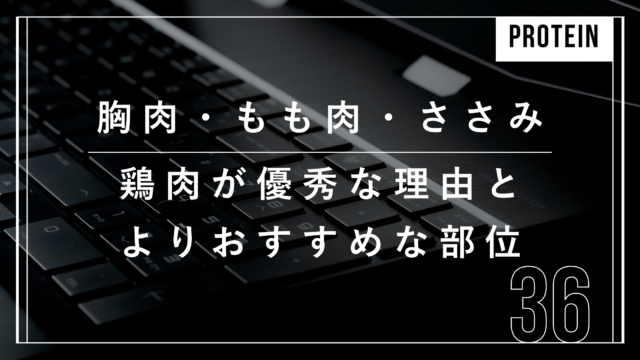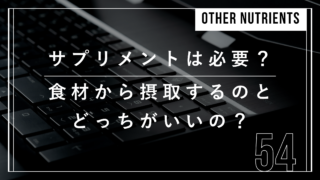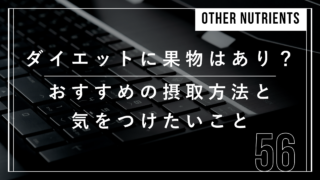「塩分の摂りすぎって、そんなに悪いの?」「むくみや高血圧と関係があるって本当?」
こんにちは!新潟県上越市・妙高市を中心に活動しておりますパーソナルトレーナーの矢坂です!
塩分は私たちの体に欠かせないミネラルですが、摂りすぎると「むくみ」や「高血圧」の原因になり、健康に悪影響を及ぼすことがあります。一方で、適量を守れば体の機能を正常に保ち、運動パフォーマンスや体調管理にも役立つため、適切な摂取が重要です。
今回は、塩分とむくみ・高血圧の関係、そして健康的な塩分管理の方法について解説していきます!
1. 塩分の役割とは?体に必要な理由
塩分(ナトリウム)は、体の水分バランスや神経伝達、筋肉の収縮などに関与している重要なミネラルです。
✅ 水分バランスの調整
塩分は、体内の水分を一定に保つ働きをしています。ナトリウムとカリウムのバランスによって、細胞内外の浸透圧が調整され、体の水分を適切にコントロールします。
✅ 神経伝達をスムーズにする
ナトリウムは、神経の信号を伝えるのに必要な電解質の一つで、筋肉の収縮や神経の働きに重要な役割を果たします。
✅ 運動時のパフォーマンスをサポート
汗をかくことでナトリウムが失われるため、運動時や暑い環境では適度な塩分補給が必要です。特に長時間のトレーニングやマラソンでは、塩分不足が筋けいれんや脱水症状を引き起こすこともあります。
一方で、塩分を摂りすぎると、むくみや高血圧の原因になるため、摂取量には注意が必要です。
2. 塩分の摂りすぎが引き起こすデメリット
① むくみの原因になる
塩分を過剰に摂取すると、体が水分を溜め込みやすくなり、むくみ(浮腫)を引き起こします。 これは、ナトリウム濃度を薄めるために体が水分を保持しようとするためです。
💡 むくみを防ぐポイント
✅ カリウムを含む食材を積極的に摂取する(例:バナナ、ほうれん草、アボカド)
✅ 水分をしっかり摂る(水を飲むことで余分な塩分を排出しやすくする)
✅ 塩分の多い加工食品を控える(カップ麺やスナック菓子など)
特に、外食や加工食品は塩分が多く含まれているため、むくみやすい人は注意が必要です!
② 高血圧を引き起こす
ナトリウムを摂りすぎると、血液中のナトリウム濃度が上がり、水分を引き込むことで血液量が増加し、血圧が上昇します。
📌 塩分過多による高血圧のメカニズム
- 塩分を摂りすぎる
- 体内のナトリウム濃度が上がる
- 体がナトリウム濃度を下げるために水分を保持する
- 血液量が増加し、血圧が上昇
- 動脈硬化や心血管疾患のリスクが高まる
💡 高血圧を予防するポイント ✅ 1日あたりの塩分摂取量を意識する(目安は男性7.5g、女性6.5g未満)
✅ 減塩食品や出汁を活用して味付けを工夫する
✅ 塩分を排出するカリウムを積極的に摂取する
日本の食生活は塩分摂取量が多くなりがちなので、日々の食事で意識して減塩することが大切です。
3. 健康的な塩分管理のコツ
① 塩分の摂取量を意識する
日本人の平均塩分摂取量は 1日約10g と言われており、世界保健機関(WHO)の推奨量(1日5g以下)の2倍 になっています。
📌 1日の塩分摂取量の目安 ✅ 成人男性:7.5g以下
✅ 成人女性:6.5g以下
✅ WHO推奨量:5g以下
※ ラーメン1杯で約6g、カップラーメン1個で約5gの塩分を含む ため、普段の食事で簡単に過剰摂取になりがちです。
② 塩分を排出する「カリウム」を摂取する
カリウムには体内の余分なナトリウムを排出し、むくみや高血圧を防ぐ 働きがあります。
💡 カリウムを多く含む食品 ✅ 野菜類(ほうれん草、ブロッコリー)
✅ 果物類(バナナ、キウイ、アボカド)
✅ 海藻類(わかめ、昆布、ひじき)
✅ 豆類(納豆、大豆)
塩分を摂りすぎたと感じた日は、これらの食品を意識的に摂取しましょう!
③ 減塩調味料や出汁を活用する
塩分を減らすために、調味料や出汁を上手に使うのも効果的です。
📌 減塩のコツ ✅ 出汁やスパイスで味をつける(例:昆布出汁、かつお出汁、ハーブ)
✅ 減塩しょうゆや減塩みそを活用する
✅ レモンや酢を使って風味をアップ
出汁の旨味を活かすことで、塩分が少なくても美味しく食べられるようになります!
4. まとめ
塩分は体に必要な栄養素ですが、摂りすぎると**「むくみ」や「高血圧」** の原因になります。
✅ 塩分の摂りすぎを防ぐポイント
- 1日の塩分摂取量を意識する(男性7.5g以下、女性6.5g以下)
- カリウムを含む食材(野菜・果物・海藻類)を積極的に摂取する
- 減塩調味料や出汁を活用して味付けを工夫する
- 水分をしっかり摂ることで余分な塩分を排出する
日々の食事で少しずつ塩分を調整しながら、むくみや高血圧を予防し、健康的な体を維持しましょう!
私について
新潟県上越市・妙高市を中心にパーソナルトレーニングを提供しています。
理学療法士の国家資格を持ち、解剖学・運動学・生理学・栄養学などの知識を活かし、体の不調改善からダイエット、ボディメイクまで幅広くサポート。